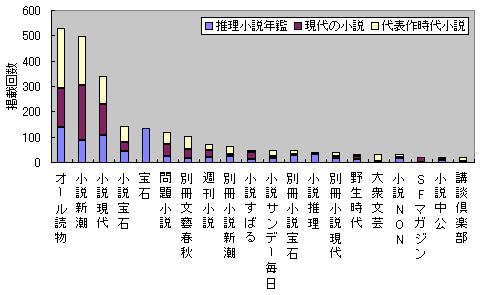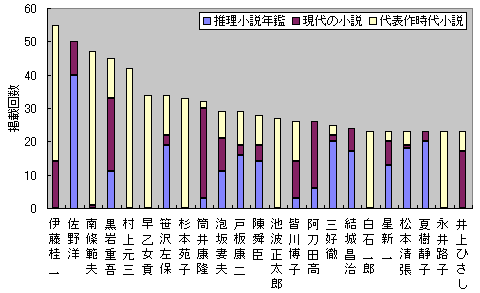
「推理小説年鑑」の最多掲載作家は佐野洋で、40回を数える。
二位の三好徹、夏樹静子がそれぞれ20回なので、おそらく今後もこの記録は破られることがないと思われる。
推理小説が現在の日本のエンタテインメントのなかで占める位置は大きい。直木賞の候補作すべてが推理小説によって占められていることもある。とすると、戦後日本で最大の短篇作家は佐野洋であるといえないだろうか。
もちろんエンタテインメントのなかには、推理小説だけでなく、歴史・時代小説もあれば、SFもある。死語かもしれないが、中間小説もある。
日本文藝家協会では「代表作時代小説」と「現代の小説」という「選集」を編纂しており、前年のエンタテインメントの状況を概観することができる。
日本推理作家協会が編纂している「推理小説年鑑」に、「代表作時代小説」と「現代の小説」を加え、作家別の掲載数を算出してみることで、戦後日本の最大短篇作家が明らかにならないだろうか。そう思ってやってみた。第1位:55回 伊藤桂一
第2位:50回 佐野洋
第3位:48回 南條範夫
第4位:47回 黒岩重吾
第5位:42回 村上元三佐野洋よりも上がいた。伊藤桂一である。
自ら「代表作時代小説」の選者に名を連ねつつ、「代表作時代小説」への掲載回数は41回を誇る(「代表作時代小説」掲載回数だけならば、47回の記録を持つ南條範夫がいる)。だが、伊藤桂一、南條範夫、佐野洋は一部のジャンルに特化した作家といえないこともない。そういう目で見ると、戦後短篇小説を代表する作家は、黒岩重吾であるといえないだろうか。
掲載回数は47回と一位の伊藤桂一に10回近くも水を空けられていながら、その内容は推理小説、時代小説、中間小説とまんべんなく網羅している。
推理小説史では、松本清張を開祖とする社会派推理小説に属する作家として記憶されているが、同じ社会派推理小説を支えた水上勉が、のちに日本を代表する純文学作家に転進したのに対し、個人的には黒岩重吾は影が薄かった。だが、彼の真価はここにあったのである。
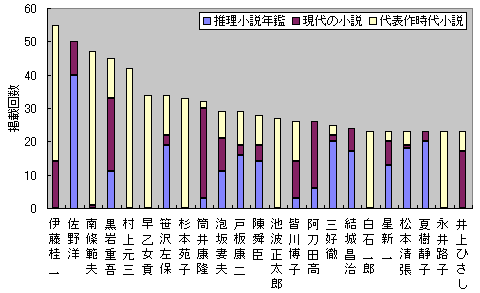
上記三つの「選集」に採られた短篇の初出誌も調べてみた。第1位:564回 オール読物
第2位:523回 小説新潮
第3位:354回 小説現代
第4位:163回 小説宝石
第5位:133回 宝石予想通り、中間小説誌が強いが、他誌を押さえて堂々の一位は老舗「オール読物」。短篇を読むなら、「オール読物」というところか。1930年(昭5)に「文藝春秋」の夏季臨時増刊号として創刊し、1931年(昭6)には月刊化、戦時中には「文藝読物」と改題されながら、1944年(昭19)には一時休刊したものの、戦争が終わった1945年(昭20)にいちはやく復刊している。特に時代小説に強みを見せた。その他のジャンルでもあなどれず、推理小説でも五位の「宝石」に匹敵するほどのヒットを誇っている。
二位の「小説新潮」は1947年(昭22)に創刊し、中間小説というジャンルは「小説新潮」が創造したといわれている。実際、中間小説に強みを見せている。
1962年(昭37)創刊の「小説現代」や、1967年(昭42)創刊の「小説宝石」は歴史が浅いためか、累計初出誌をとると分が悪い。が、とりわけ「小説現代」の健闘はめざましい。こうなると、中間小説誌の書誌が欲しいところだが、現在のところ、文藝年鑑のバックナンバーを紐解くしかないのだろうか。
五位にランクしている「宝石」は推理小説のみの掲載。1964年(昭39)に廃刊しているのにもかかわらず、上位にランクしているのは、戦後探偵文壇黎明期の荒稼ぎが効いているといえばいいすぎか。
上位五誌で、全体の六割前後を占め、寡占化著しいという結果が得られた。